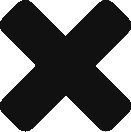観想の空間 マンダラ・尾道・曼荼羅
を読む。
代表的なマンダラ絵図を紹介した後、マンダラを意識した現代アートの試みが載せられていて、マンダラに関する考察の文章がいくつか載せられている。
マンダラのための原形態 植田信隆 が面白い。説明を読むとこのように理解できる。
エレメント=四大(地、水、空気、熱)地と水が根を生じ、水と空気で葉が繁り、空気と熱で花を咲かせる。桜は、真ん中のプロセスを通り越して根と花だけの状態で見えるから、余計大きなエネルギーを吸い上げる必要があり、そのため、上部がより高められた命を感じられ、低みにはより粗雑で死滅した物質があるように感じられる。満開の桜の花に、植物の本質である、生命の蕩尽をもっとも感じることができる。
建築としての曼荼羅(ひずめ あきお)の一節の抜粋
「なかでも曼荼羅はきわめて成熟した建築といえる。それは密教僧の住む家にほかならない。(中略)彼らは瞑想と称しているが、実は曼荼羅の内部空間に実際的に生活しているも同然だ。(中略)触覚的な視覚を有するものならば、実際に建築せずとも設計図の中で十分生活できるのである。(中略)当時知られている限りの幾何学を援用して、無数の要素が有機的に階層化され、グルーピングされる。(中略)もし空間がフラクタル幾何学を学んでいたら、現存するような曼荼羅の形式を取っていなかっただろう。」
スマートフォンは現代のマンダラとなったのか。いや、スマートフォンには奥がない。しかしすでに空間がある。建築が精神の住処であり続けるためには、もはや空間を追求するのではなく、無限の奥、スケールを横断するの拡大縮小性、をめざすべきではないだろうか。