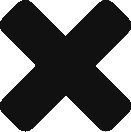都内の住宅の完了検査を無事終えて、大阪へ。西脇の家の地鎮祭と打合せに参加するためである。
この日移動日で、少し時間ができたので、大阪でやっている美術展をハシゴ。
まずは国立国際美術館、日常の常。映像中心の展示となっており、戦争、災害に身を置くことを迫られる体験。こちらの美術館は初めて立ち寄るが、常設展もなかなか充実。空間は設計集成に載ってそうな、吹き抜け介して各階の展示室にアクセスする、標準だがダイナミックな空間。
次に中之島美術館へ、日本美術の鉱脈展。
江戸、室町、明治、縄文と、時系列を横断しながら各時代の有名な画家たちを取り上げていた。説明がポップで切り口が明快、大学時代にとった美術史の授業を思い出しながらも新しい発見がたくさんあった。芸大による若冲の絵の復元が迫力があった。
こちらの空間は最上階の展示空間と地下のレストラン、あとはそれを包む大きなエントランス空間といった感じで、吹き抜けが大きすぎると吹き抜けではなくなるという新しい発見だった。
国立国際のほうは展示室に穿かれた竪穴としての吹き抜けに対し、中之島のほうは大空間に展示室が浮遊するイメージ。
その日のうちに西脇に移動して、翌日早朝西脇の地鎮祭の現場へ。
工務店の方がテントや縄張りまで手際よくやっていただいてた。東京で最近ここまでしっかり設営する地鎮祭をなかなか経験しない。
晴天に恵まれ(暑かったですが)地鎮祭が無事終了。降龍の儀と昇龍の儀のときに偶然風が幕を吹き上げ、神様を感じられた。