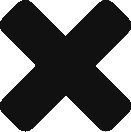量子の社会哲学-革命は過去を救うと猫は言う 大澤真幸
購入してしばらく放置していたこの本を再度読んでみる。
自然科学と、遠近法の関係について語っているあたりが興味深い。
古代、中世、近代の遠近法について述べている。古代は、角度の遠近法だった。各物体を見るときの目の動きの角度(球面上)を、平面に投影して作図するため、消失点ではなく、消失線が現れる。中世では、遠近法が影を潜め、述事する物体を並列的に並べ、その間に空間を設けている。空間の概念が芽生えたと説いている。ルネッサンス期に成立した近代の遠近法は、空間という概念が成立し、物体のあるなしに関係なく、空間に平面の膜を想定して、そこに投影することで作図される。遠近法の移行は、空間という抽象的な認識の獲得と並行している。
アリストテレスは、例えば土は下に、火は上に移動しようとし、水、空気はその間と、世界を天上界、地上界に分別して、認識している。これはまさに物体と、物体のない空間を分けて考える古代の遠近法と一致する。ニュートンの万有引力をはじめとする一連の自然科学の定理は、まさに世界を完全に均質的な空間としてみる、近代の遠近法そのものだった。そしてそれには、無限小の空間から外部を見る、世界の外部への撤退が必要とし、法則の外に立ち、客観視する視点を説いている。同じ時期の絵画にそれを示唆する試みがなされており、
ベラスケスのラス・メニーナスの、消失点に位置するカーテンを引く従士は実は画家自身であり、カーテンの向こうがその超越的な外部と対応している。
宗教の概念とも関連付けているあたりも面白い。
聖なるものや超越的なものへの厳格な追及が逆に世俗化への転換してしまう逆説、ヘーゲルが、「抽象的普遍から具体的普遍への転換の論理」と名付けているが、資本主義、科学革命、絶対王政の成立がいずれもその流れに乗っている。
ニュートンの唱える万有引力に説得性を持たせるために、つまり間に媒介のない任意の2つの物体の間に引力が発生ことを説明するために、そこに神の常なる介在を認めざるを得ないとした。それには、すべてを満たす「光」という暗黙の仮定が必要であった。これは一見、神は、どの瞬間においても、自然に働きかけているように見える。これは、デカルト的、初期設定する神という概念と対立するが、デカルト的因果論的、機械論的な言説に物理法則の補完を与えたのもニュートンである。神のちからである光が、のちに、ただの媒介する物体であるエーテルに、変更されていく。
プロテスタントの、もっとも敬虔とされるカルヴァン派の予定説の概念が、結果的に最も冒涜的とされる資本主義をもたらす駆動力となった、という矛盾をはらんでいる。全能の神であれば途中で修正を加える必要がなく、最初の設定だけで事足りるという概念がプロテスタントの根底にあるが、それが結果的に神の不在へつながるのである。
そして、世俗化する王の身体によって、王の政治的身体という、抽象的な普遍性が獲得される。ラス・メニーナスでは、見る人に王の目線に立たせることで、鏡に映る王(政治的身体である王)を認識させている。
つづく